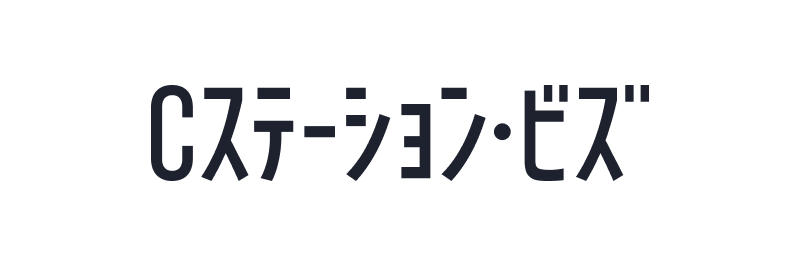講談社と広告主の共創で生まれた広告企画を対象に、優れた企画を選出する「講談社メディアアワード」。今年も、10月30日(木)に開催するビジネスイベント「講談社メディアカンファレンス 2025」内にて、贈賞式が行われます。
今年の審査には、昨年加わった4名に加え、新たに広告プランナー・クリエイティブディレクターとして活躍する市川晴華さんが参画しました。
審査に先駆け、審査員代表を務める『宣伝会議』編集長・谷口優さんがインタビューを実施。市川さんが語る、プランナーという仕事の本質、昨今の広告に感じている危機感とはーー。審査に向けた想いとともに伺います。
大きな構想を描き、信頼関係でつくり上げていく。市川晴華が語るプランナー像
谷口 CHOCOLATEのプランナーとして活躍している市川さん。まずは、市川さんが「プランナー」というお仕事をどう捉えているのか伺ってみたいと思います。
市川 私にとってプランナーは、「構想を練る人」です。構想に特化しているからこそ、手を動かす人たちが「そんなの無理だよ」と感じるような無邪気なアイデア——いわば「机上の空論」を思い切ってつくることができるのが、この仕事の醍醐味だと思っています。着地できるかどうかはわからないけれど、まずは1回大きな構想を描いてみる人。これが、私が思うプランナー像かもしれません。
ただ、実際に自分が手を動かすわけではないので、1人では完結させられない仕事でもある。つまり、無人島に行ったら私は何もできないんですよね(笑)。
だからこそ、一緒に仕事をするクリエイターの方々へのリスペクトが何より重要だと思っています。お願いする立場だからこそ、どうすれば気持ちよく一緒に作れるか、どうすればメンバーのモチベーションを高めていけるのか……そうしたコミュニケーションの仕方を考えることも、プランナーの重要な役割のひとつだと感じています。
1990年生まれ。広告を中心に、SNSからTVCMまで幅広く手がけるプランナー。読売広告社にもパートナースタッフとして所属。マスとの連動性やタイムライン上の細部にまで目を配り、新たな表現を探り続けている。代表作に、サントリーペプシ「本田とじゃんけん」「クールポコ」、イエローハット/ピザハット/リンガーハット「ハット首脳会談」、中京テレビ「ヨンと鳴く犬」などがある。
谷口 「クリエイターへのリスペクト」もその1つだと思いますが、チームメンバーとの信頼関係を構築していく際、市川さんが意識されていらっしゃることはありますか?
市川 お仕事をご一緒する相手について、徹底的に調べてからご依頼するようにしています。たとえば映像制作の仕事で初めてご一緒する監督さんがいた場合、その方の過去のお仕事を拝見し「この作品のここが好きです!」と、伝えるイメージです。自分がその人の何に惹かれ、なぜ今回お願いするのか。その理由をきちんと説明することは常に意識しています。
一方で最近は、「自分を知ってもらうこと」も大事だと感じています。プランナーって、意外と相手からどういう人か知られてない場合が多いし、お互いを知らないとやはりコミュニケーションが取りづらいんですよね……。
だからこそ、自分がどういう人間で、どういう仕事をしてきて、何に興味があるのかなど、しっかり自己紹介をするようにしています。自分のことを知ってもらえると、ぐっと距離が縮まるし、対等な関係性が築きやすくなる。これもある種、相手へのリスペクトのひとつだと思っています。
消費者の声と自分の原体験から、ブランドの「人格」を引き出す
谷口 市川さんの企画を拝見していると、どれも企業やブランド、商品の持つ「人格」みたいなものが、とても魅力的に表現されていると感じます。企業やブランドの魅力を引き出すために、どのような調査・分析をされているのでしょうか。
大学卒業後、宣伝会議に入社し、編集部に配属。月刊『宣伝会議』副編集長を経て、2007年10月より編集長に就任。現在は、宣伝会議の出版、メディア事業のマネジメント全般に関わる。社会構想大学院大学の准教授も兼任。
市川 一般的によく言われていることではありますが、私はまず、SNSやAmazon、楽天のレビューなどを巡って、消費者の方々がそのブランドや商品についてどんな感想を持っているのかを徹底的に調べるようにしています。ネット上にあるリアルな声から「このブランドや商品は今、世間からこう見られているんだ」と感じ取ることができたり、SNSやサイトを巡っていると「ここにファンコミュニティがある」ということも把握できたりします。ある意味、出版社でいう「読者層」を知ることに近いかもしれません。
谷口 そうした“世の中の声”を丁寧に拾い上げるところから始めるのですね。
市川 はい。「世間からこういう風に思われているから、こういう人格で表現してみよう」と考えていくイメージです。
もうひとつ、自分自身の“原体験”も、ブランドの魅力を引き出す上では大切だと思っています。たとえば、担当している、「ペプシ」(サントリー)の案件。私にとって「ペプシ」は、子どもの頃に見たペプシマンのCMや、ボトルキャップを集めていた記憶があって、「ちょっと笑える」ようなブランドイメージがずっと残ってるんです。今の世の中のイメージとは少しずれているかもしれないけれど、自分の原体験、つまりn=1の感覚を信じてブランドと向き合うようにしています。
谷口 世間の声だけでなく、ご自身の体験や感覚も大切にされているのですね。まるで人付き合いのように、企業やブランドと向き合っているのだと思いました。

市川 そうかもしれないです。「アロンアルフア」(東亞合成株式会社)の案件も、まさに実体験が企画の起点になっています。初めて使ったときの驚きや感動が、ずっと心に残っていて…。実際に自分で試したり、使ったりしたときの感覚や感想はすごく大切にしています。そのほうが、自然と企画に気持ちが乗るんですよね。
また、自分の体験だけでなく、普段から“人の行動”を観察することも意識しています。以前、駅の自販機で飲み物を買ってその場で飲み干したとき、ゴミ箱を探して、きょろきょろしてしまったことがあったんです。一般的には自販機の隣にゴミ箱があると思いますが、見つからなかったんですよね。そのあと駅のベンチにいたら、同じように飲み干してしまった人が、私と全く同じ動きをしていて。「やっぱりそうなるよね」と、すごく面白かったんです。
そうした何気ない行動の中にも企画のヒントがあると思っているので、人々の行動にはこれからも注目していきたいですね。
広告がブームをつくれない? ますますひろがる広告への「ネガティブ」な感情。
谷口 広告業界全体のこともお聞きしてみたいと思います。企画だけでなく、広告賞の審査員を務めるなど、さまざまな立場から広告に関わっている市川さんですが、今の広告業界をどのように見ていらっしゃいますか?
市川 私はキャリアの出発点がSNSの仕事だったので、その視点から見ると、広告がブームの“先駆者”になりづらくなっているという感覚がありますね。
以前は、広告がブームをつくってきたと思うんです。たとえば、あるCMで流行ったダンスをみんなが真似して踊る……そういう構図がありましたよね。しかし今は、SNSやネットの中で生まれた流行を広告が後から取り入れていく、構図になっていることが多いと感じています。もちろんそれ自体が悪いことだとは思いませんが、少し寂しいですよね。
谷口 広告がブームをつくれない……。その背景には、何があると思いますか?
市川 広告に対する「ネガティブな感情」が高まっていることも、要因のひとつだと思います。
これも私の実体験なのですが、通っているジムの若いトレーナーさんと話していて、驚いたことがあって……。あるとき「私、面白いCMが好きで、広告の企画をやっているんです」と話したところ、「面白いCMってなんですか?」と言われたんです。本当に衝撃でしたね(笑)。その方に限らずですが、特に若年層では、広告は「面白いもの」というよりも、「邪魔なもの」という認識が強まっていると感じました。
たしかに媒体によっては、見ていた動画がいきなり途切れて広告がインサートされてくるものもあります。そうなると、“楽しい時間を中断するもの”として嫌悪感を持たれてしまいますよね。こうしたプラットフォーム側の構造的な問題も大きいのだと思います。
市川 一方、テレビ番組には「続きはCMのあとで!」というような、数秒の橋渡しがありますよね。あのちょっとした前置きがあるだけでも、広告に対する心理的なハードルは少し下がっていたのかもしれません。広告の中身だけでなく、ユーザビリティも含めた体験設計まで考えていかないと、広告と人々とのあいだにある分断はこれからますます広がってしまうのではないかと感じています。
谷口 たしかに、広告に対する消費者の価値観は変わっていますよね。私くらいの世代だと、面白い広告がたくさんあって、広告を見るのが楽しみだった記憶があります。今は、メディアとの接し方自体が変わってきているのかもしれませんね。
市川 その変化は、宣伝会議の講義で学生さんたちと関わるときにも感じます。私はてっきり広告業界に興味がある人が受講してくれていると思っていたのですが、「広告をやりたい」というより、「企画がしたい」とか「SNSで動画を作って発信したい」という理由で受講される方が増えている印象があります。今は、アウトプットの選択肢が広告以外にも無数にあるので、「何かをつくりたい」と思ったときに、広告が選ばれない。そうした現実をすごく感じますね。
だからこそ、広告業界の面白さ、広告そのものの面白さを改めて伝えていきたいと思っています。そのためには、私自身が「広告だから面白い」と感じてもらえるものをしっかり届けていく必要があるなと。オリジナリティのある面白い広告を発信することができれば、広告が今一度ブームをつくる存在になれると信じています。
個人の発想が、多くの人の承認を経て社会に届く。その「スケール感」が面白い
谷口 「広告だからこその面白さ」を追求し続ける市川さんにとって、「広告の面白さ」って、どんなところにあると思われますか?
市川 私が広告を面白いと思うのは、たくさんの人の合意形成のもとでできているからなんです。たとえば、CMを見て「この大企業が、この内容にOKを出したんだ!」と感じることありませんか? そうした背後にある組織の巨大なスケールを感じられるのが、広告の面白いところだと思っています。
谷口 広告は多くの人の“ハンコ”が押されてできあがるものですが、市川さんが大切にしているのは、n=1としての自分の感性でもある。この、2つの視点を両立させている点が興味深いです。
市川 そこがまさに面白いんですよね! 自分が面白いと思って企画した超個人的なものを、多くの人がハンコを押して、企業のコーポレートアイデンティティとして発信されるというスケール感は、広告ならではだと感じています。
その1つが、中京テレビさんで担当したTVCM「ヨンと鳴く犬」という企画です。「中京テレビは4ch」ということを訴求したいというお題に対して、10年前にネットでミームとなった一般の方が撮影した「ヨンという鳴き声の犬」の映像を、許可をとり当時の画質のままCMとしてテレビで放送しました。ブランドCMとして流すことで、企業の懐の深さを感じるものになったと思います。
スケール感は、広告ならではの面白さのひとつです。でも、広告だからこそできる表現や仕掛けは、まだまだたくさんあると思っています。「広告にしかできない面白さとは何か」という問いは、これからもずっと考え続けていきたいテーマです。

「手探り感」で生まれた企画は、きっと面白い
谷口 ここまでお話を伺ってきて、プランナーは編集者とすごく似ていると感じました。どちらも1人では完結しない仕事ですし、正解が見えない中でも「まずやってみる」という姿勢がありますよね。講談社メディアアワードに集まる企画も、そうした編集者の手探りから始まったもので、市川さんと通じる部分があるように思います。
市川 たしかに、編集者とプランナーは似ているかもしれないですね! 私も「まずはやってみよう」というチャレンジ精神はすごく大切にしています。広告の世界は、手探りから始まった企画が結果的に大きな反響を得た、ということも多いので共感するところがたくさんありそうです。
谷口 きっと市川さんが「面白い」と感じるような企画に出会えると思います。それでは最後に、市川さんが講談社メディアアワードに期待していることや、楽しみにしていることについてお聞かせください。
市川 講談社が仕掛ける企画は、媒体の読者はもちろん、広告主のブランドにもファンがいますよね。両方に向けて企画を成立させるのって、実はかなり難易度が高いことだと思うんです。ですが、過去の企画を拝見して感じたのは、谷口さんがおっしゃる通り「手探り感」で飛び越えていく身軽さのあるものばかり。見ていてすごくワクワクしました。読者視点で雑誌やコンテンツをつくってきた編集者さんや営業の方が企画しているからこそ、私たちが思いもよらない企画が生まれるのだと思います。今回はどんな企画に出会えるのか、本当に楽しみですね。