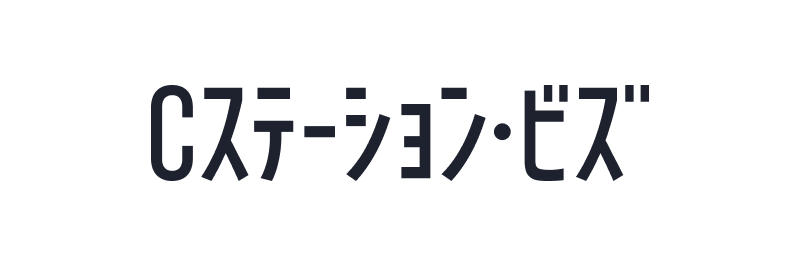創業から100年余、日本の石油産業を支えてきた出光興産(以下、出光)。同社は今、「DE&Iの深化」を成長戦略の中核に据え、多様な人材が力を発揮できる組織づくりを進めています。
なかでも象徴的な取り組みの一つが、女性活躍の推進です。2024年には、製造現場で働く女性社員の声からはじまった職場環境の変化について、クーリエ・ジャポンで発信。社内外で大きな反響を呼び、「現場の今」を知ってもらう手応えを感じたといいます。
DE&Iに取り組む背景や社外発信の意義、そして見えてきた成果とは……。クーリエ・ジャポン ブランドディレクター・河野仁見が、出光興産のDE&I推進室長・大津麻衣さんに伺いました。
クーリエ・ジャポン掲載記事はこちら>>
「ひとりの女性が声をあげたことで、出光興産の製造現場は変わった」
女性活躍推進は“土壌づくり”から。出光が挑むDE&I視点の企業変革
河野:以前『クーリエ・ジャポン』で、製造現場の女性活躍についての記事を掲載させていただきました。その際も多彩な取り組みを伺いましたが、改めて貴社がDE&Iに注力されている理由を教えていただけますか?
大津:私たちは創業以来、燃料油を中心に、生活に欠かせないエネルギーの安定供給を担ってきました。しかし、社会全体が「脱炭素」へと向かういま、企業としても大きな転換点を迎えています。変革のためには、これまでの枠組みにとどまらず、多様な背景や経験を持つ人の力が欠かせません。DE&Iの視点を持ち、多様な人の価値観や強みを掛け合わせることが、新たな価値を生む原動力になると考えています。
河野:そのなかでも、女性活躍推進に力を入れていらっしゃいます。そこにも何か理由があるのでしょうか。
大津:はい。女性活躍推進は、さまざまあるDE&I施策のなかでも重要なテーマです。
少子高齢化により労働人口が減少しているいま、女性活躍は欠かせません。とはいえ、当社のような石油業界は、社員の約85%が男性という現状があります。だからこそ、女性が安心して能力を発揮できる環境をどう整えていくかは、非常に大きな課題でもあるんです。
また、女性が働きやすい職場を整えることは、結果的に誰にとっても働きやすい職場づくりにつながります。たとえば、育児や介護そして病気との両立支援は、性別を問わず多くの人にとって意味のあるものですよね。そういった視点を持って、制度だけでなく職場全体のあり方を見直す取り組みを進めています。

大津:ただ、こうした取り組みを始めた当初は、「なぜ女性ばかりなのか」といった声が社内にあったのも事実です。それでも「なぜいま女性活躍が必要なのか」を粘り強く発信し続け、職場全体の理解度を高めることから取り組んできました。
河野:多様な人を支える制度だけでなく、まずはその土台となる“土壌づくり”に力を入れてきたということですね。
大津:そうですね。制度や研修の場を整えて「頑張れ!」と本人に伝えても、周囲の理解や後押しがなければなかなか前に進みません。ましてや、本人が「やってみよう」と思った瞬間に、その思いが潰されるようなことがあっては絶対にいけない。だからこそ、土壌づくりがとても重要だと考えています。
とはいえ女性の役職者比率はまだ低く、数字だけを見るとまだ道半ばかもしれません。それでも職場の空気感や社員一人ひとりの意識といった土壌の部分は、着実に変わってきていると実感しています。
女性たちの声が、製造現場の変化を生み出す力になった
河野:『クーリエ・ジャポン』の記事で私が特に印象的だったのが、製造現場の女性たちを中心に、多様な立場の方が協力してムーブメントをつくり上げていたことです。本社や人事部門、かつて副所長として勤務し、課題を感じていた男性社員など、さまざまな人が「一緒に変えていこう」という思いで関わっている。現場の声を周囲が支える、そんな風土があるのだと感じました。
大津:製造現場の意識も、ここ数年で徐々に変化していったものだと思います。
技術職の女性は増えつつあるものの、製造現場はまだまだ男性比率が高く、女性が使いやすい備品や働きやすい職場環境が十分に整っていないという課題がありました。そうした中で、現場の女性たちが自ら声をあげ、その声がきちんと受け止められるようになってきた。少しずつですが、「女性だからこそ見える課題」や「改善への提案」が自然と受け入れられる空気が育ってきたのだと思います。
ここまで変化がひろがったのは、4つの製造拠点が連携し、女性たちが声を出し合うようになったことが大きいですね。しかも、彼女たちの声は「現場の女性がより働きやすい環境をつくりたい」という前向きな提案なんです。仲間が活き活きと活躍することを願って生まれた声だからこそ、製造現場全体の風土を変えていく原動力になったのだと感じています。

河野:現場に貢献したいという女性たちの声が、「変化を生み出す力」になっているのが素晴らしいですよね。
大津:いまでも、4つの製造拠点が連携する会議は毎月行われていて、現場で出た課題を共有し合いながら、一つひとつ解決に向けて動いています。実際に、『クーリエ・ジャポン』の記事で取り上げたバルブの課題については、改善に向けて具体的に動き始めています。
河野:設備のバルブが重く、女性の腕力では操作が難しい場面があるという課題ですね。毎回、男性の手を借りなければならない状況に申し訳なさを感じるという女性たちの声も印象に残っています。着実に改善が進んでいるのですね。
大津:そうなんです。記事掲載時はまだ特別な取り組みという印象もありましたが、課題を吸い上げて解決していく動きはもはや特別なことではなく、日常の一部になってきています。これからも現場の声を活かしながら、改善を続けていきたいと思っています。
広く、深く、出光らしさを届けるために─『クーリエ・ジャポン』で発信した理由
河野:今回、製造現場の女性活躍推進について、メディアを通じて社外に発信しようとお考えになった背景をお聞かせください。
大津:なによりも、多くの方に私たちの取り組みを知ってほしいという思いが強かったです。これまでもコーポレートサイトやプレスリリースで発信してきましたが、どうしても情報が届く範囲に限りがあります。より広い層に伝えるために、メディアを活用して発信する必要があると感じ、今回『クーリエ・ジャポン』にお願いすることにしました。
河野:数あるメディアの中から『クーリエ・ジャポン』を選んでいただいた理由を、詳しくお聞かせいただけますか。
大津:理由はいくつかありますが、まず『クーリエ・ジャポン』の読者層に惹かれました。SDGsやDE&Iといった社会的テーマに関心の高いビジネスパーソンが多く、男女比もバランスが取れているため、広く発信したいと考えていた私たちにぴったりだと感じました。
また、DE&I特集を組んでいらっしゃったことも理由のひとつです。特集の中で各企業の個性やカラーを尊重しながら丁寧に紹介している点は非常に魅力的で……。取り組みを深く理解してもらえるだけでなく、出光らしさも伝えられると思いました。実際に公開後は、社内外から「記事読みましたよ」と声を掛けられることが多々ありましたね。
河野: 社内だけでなく、社外からも嬉しい反応があったのですね。たしかに貴社の取り組みは、同じような課題を抱える企業の方々にとって大きなヒントになると思います。
大津:製造現場を持つ企業は、どこも似通った課題を抱えているんですよね。異業種との交流会などで他社から「どうやって進めているのか」と尋ねられることも多く、その関心の高さを実感しています。エネルギー業界の関連企業が集まって行われた女性活躍推進に関するワーキンググループでも発表の機会をいただき、当社の取り組みを詳しく説明することもありました。こうした発信を通じて、業界全体がより良い方向へ進んでいければ嬉しいですよね。

大津:また、社内でも反響が大きく、社員が投票する表彰制度で「製造現場の女性活躍推進の取り組み」が、職場風土貢献部門のグランプリを受賞しました。クーリエの記事は、取り組みの詳細が細かくまとまっていたので、エントリーの際に参考資料として活用させていただきました。
河野:社内PRにも役立っていると聞けて、メディアとしても嬉しく思います。読者の中には、出光さんの取り組みに興味を持って「こんな雰囲気の会社なんだ」と感じてくれる方もいるかもしれませんね。そうした意味でいえば、採用活動にも良い影響がありそうです。
大津:実際に、採用活動にも活用しています。とくに、今回の記事とあわせて制作した動画コンテンツ。女性社員の働く姿や、それを支える周りの社員の声を丁寧に紹介していて、職場の雰囲気や価値観が伝わる内容になっています。応募を検討されている方にとっては、文章だけでは伝わりにくい部分を感じ取ってもらえるものだと思いました。この動画は、採用サイトにも掲載しています。
河野:生き生きと働く様子や、製造現場のリアルな空気感が動画を通じて伝わってくるので、職場を理解するうえでとても効果的ですね。
大津:そうですね。余談ですが、動画の制作過程については、社内報でメイキング記事として紹介しているんですよ。動画のアピールだけでなく、撮影の裏話や動画では拾いきれなかったスタッフの声なども掲載しました。取材を受けたスタッフたちからは、「自分たちのやっていることに自信が持てた」という声も聞きました。多方面で良い影響があったと感じています。
「推進課」から「推進室」へ。DE&Iの深化を支える「対話」の文化
河野:ますます取り組みが広がっている中で、今年4月には「DE&I推進課」から「DE&I推進室」へと体制を強化されたと伺いました。どのような狙いがあるのでしょうか。
大津:組織を“課”から“室”へと改編したのは、よりスピード感を持って取り組みを進めるためです。そして、斬新で多様な意見もダイレクトにマネジメントへ届けやすくなりました。これは、会社としての本気度の表れでもあると思っています。
現在は私を含め9名の専任社員が、多岐にわたる施策を主導しています。たとえば、アンコンシャス・バイアスへの気づきを促す「アンコン対話」や、エクイティ(公正性)の必要性を共に考える「エクイティ座談会」など、対話を通じて意識変容を促す取り組みが中心です。
河野:お話を伺っていると、取り組みには一貫して「対話」が中心にあると感じます。出光さんのDE&Iは、現場の声をすくいあげながら進んでいるのですね。
大津:対話を通して一人ひとりの言葉を聞くというのは、DE&Iの本質でもありますからね。当社では1970年から「自問自答会」という名の対話と内省の場が、現場を中心に脈々と続いてきました。対話を大切にする文化は、「出光らしさ」のひとつなのかもしれません。先日も製造部門でタウンホールミーティング(経営層と従業員の直接対話の場)を実施したばかりですし、女性社員のキャリア支援を目的としたメンタリングプログラムでも「対話」を重要視しています。
河野:企業横断で実施されている「クロスメンタリング」も、まさに「対話」を軸にした取り組みですよね。
大津:はい。「クロスメンタリング」は、企業の垣根を越えて、社外の経営幹部がメンター、女性役職者がメンティとなって対話を重ねるプログラムです。女性役職者の自律的なキャリア形成を支えると同時に、多様な人財が企業を超えて学び合い、育て合うことによって、ジェンダーギャップの解消を加速させることをめざしています。
ただ、こうした取り組みや施策を推し進めるためにも、それを受け入れる土壌が欠かせません。当事者でない社員が、どれだけ“自分ゴト”として捉え、周囲を思いやれるか。その意識の醸成があってこそ、本質的な変化は生まれるのだと思います。
だからこそ私たちはこれからも「対話」を通じて、土壌を育てていくことに力を注いでいきたいと考えています。
発信することは、企業イメージに対するアンコンシャス・バイアスをなくすきっかけにもつながる
河野:『クーリエ・ジャポン』では、貴社のDE&Iに関する2回目の記事企画も進めています。次回は、出光さんが大切にされている「対話」の考え方や、新たな動きについても深く掘り下げていけたらと思っています。お話を伺うのを、今から楽しみにしています!
それでは最後に、改めて「発信し続けることの意義」について、どのように感じていらっしゃるか教えていただけますか?
大津:かつては「良いことをしていれば、誰かが気づいてくれる」と思っていましたが、今は、きちんと伝えることの重要性を強く感じています。とくにDE&Iは、採用や投資といった観点からも注目度が高いテーマです。弊社でも、社外取締役と副社長による対談形式の投資家の皆様向けセミナーでDE&Iをテーマに掲げるなど、対外的な発信の場を増やしているところです。
河野:たしかに、DE&Iは企業の価値を測る指標としても重要ですし、発信の積み重ねが評価にもつながっていきますよね。
大津:そうですね。企業としての姿勢を社外に伝えていくことは、採用や取引先との信頼関係にもつながっていくと感じています。特に私たちの業界は、「男性中心で保守的なのでは」といった先入観を持たれがちです。だからこそ、「私たちがどんな会社なのか」だけでなく、「どう変わろうとしているのか」という姿も、継続的に発信していくことが重要だと思うんです。
今回のように、『クーリエ・ジャポン』のようなメディアに取り上げていただけることで、そうしたアンコンシャス・バイアスをやわらげる一歩になるのではないかと期待しています。