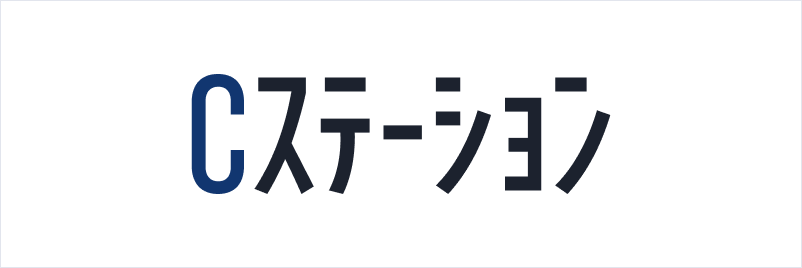1952年、アメリカで誕生。1970年に日本上陸。現在、全国で約1200店舗を展開するファストフード・チェーンの日本ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)。創業者カーネル・サンダース氏の想い「おいしさ、しあわせ創造」を企業理念に掲げ、食を通じた地域貢献にも同社は積極的に取り組んでいます。その活動のひとつである、こども食堂等へのチキンの寄贈について、同社の経営戦略部 サステナビリティ推進課 係長 本多翔太さんに、取り組みの背景、想いを聞きました。
創業者の意思を継承し、地域社会への貢献を重視
——KFCの創業者といえば、カーネル・サンダース氏です。SDGsへの取り組みに関しても、同氏の想いは時代を超え、反映されているのでしょうか?
本多 KFCは、企業理念である「おいしさ、しあわせ創造」のもと、創業者カーネル・サンダースから受け継いだレシピを現在も使用し、店舗で手づくり調理し、安全安心な商品を提供することにこだわっています。
日々、全国約1200店舗を通じて、多くのお客さまの“食”に関わる企業として、社会的責任を強く感じるとともに、SDGsが掲げる「持続可能な社会の実現」は、食の持続可能性も重要なテーマのひとつであると捉えています。
また弊社では、地域社会とともに事業を成長させることを大切にしています。背景には、創業者が遺した「地域のお客さまは家族」という言葉があり、その想いを継承し、現在に至るまで弊社の指針となっています。

——企業理念は「おいしさ、しあわせ創造」。そこに込められた想いを教えてください。
本多 弊社の企業理念は、弊社の使命として掲げているものです。日々のお食事を通じて、「おいしさ」でお客さまと、このビジネスに関わるすべての人の「しあわせ」を「創造」する。その「しあわせ」を社会全体に向けて、より広く、より多くの方に届けていくことでKFCの事業も成長していくと考えています。
——KFCを含め、ファストフードチェーン店は利便性が高いからこそ、SDGsの掲げるゴールと密接につながっている印象です。
本多 そうですね。食品を扱う企業として、フードロスや廃棄といった食に関わる課題は、私たちにとって非常に重要なテーマだと考えています。
日々の店舗運営の中でも、いかに食品ロスを最小限に抑えるかは意識しています。KFCのサステナビリティでは、「店舗と地域の絆」を重要なキーワードに据えているのですが、本日お話しさせていただく、チキンの寄贈もその一環となります。
調理済みチキンを冷凍保存し、食材としてこども食堂等に寄贈
——寄贈には「閉店時にどうしても残ってしまうチキン」を活用しているそうですね。そもそも、閉店時になぜチキンが残ってしまうのでしょうか?
本多 店舗で手づくり調理しているこだわりの「オリジナルチキン」は、創業から大切にしてきたKFCブランドの資産です。主力商品である「オリジナルチキン」は、いつでも提供できる状態にしています。一方で、調理には一定の時間を要するため、あらかじめ販売状況を予測して準備する必要があります。そのため、どうしても閉店時にチキンが残ってしまうことがあります。
ですが、まだおいしく食べられますし、廃棄することは、店舗従業員としても決して気持ちのいいことではなく、長らく課題となっていました。“もったいない”という思いを店舗従業員は抱えており、私個人としても解決したいと考えていました。
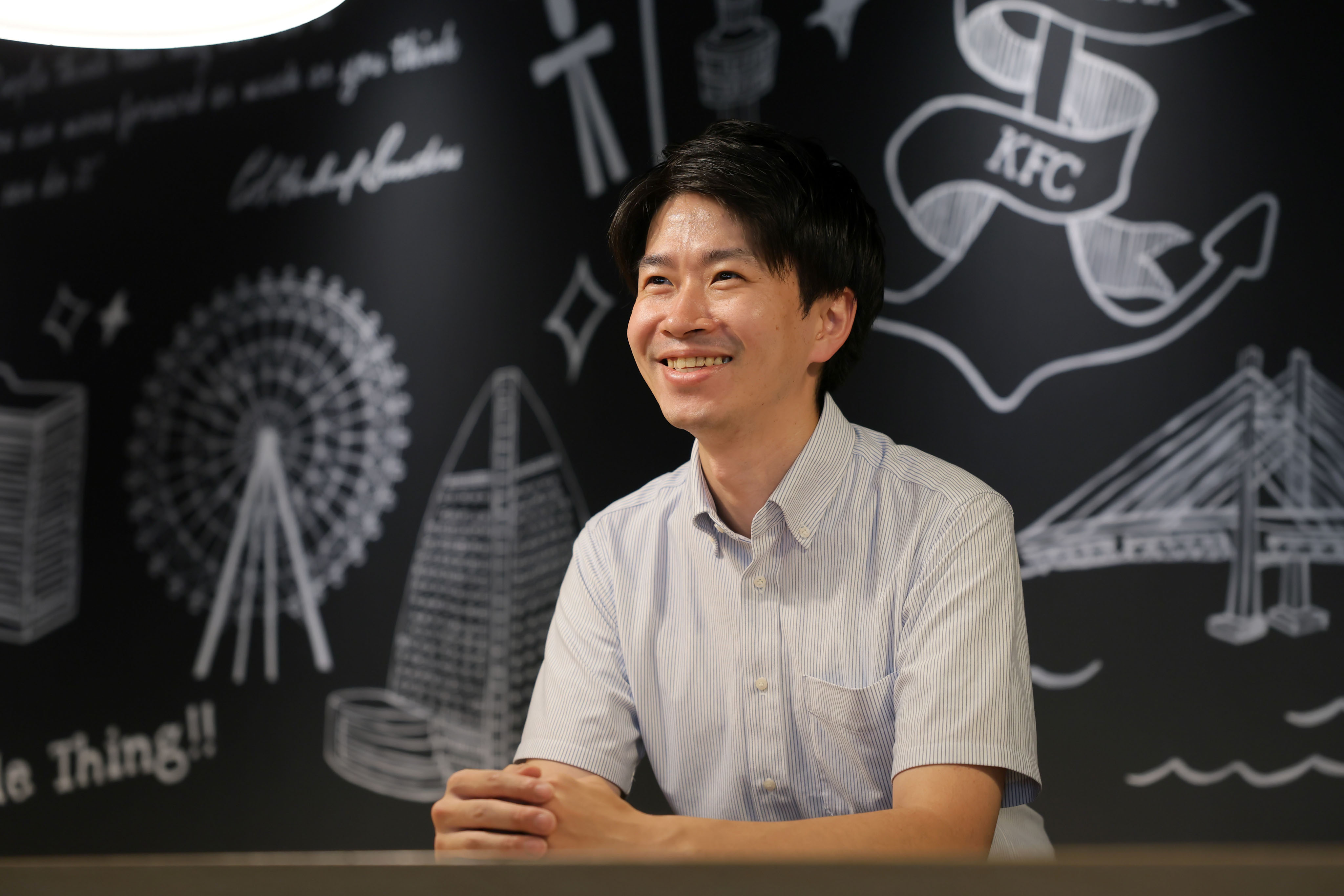
——チキンの寄贈は、提供側も「しあわせ」になれる取り組みなのですね。取り組みをスタートした経緯について、詳しく教えてください。
本多 はい。2017年、本社を横浜市に移転した際、同市と包括連携協定を締結しました。対象分野のひとつに「こども・青少年の育成に関すること」という項目があり、取り組み内容を検討するなかで、定期開催されているグローバル会議において、イギリスなど他の国々の店舗が取り組んでいるチキンの寄贈事例と出会いました。
その日、お店で残ってしまったチキンを冷凍保存しておいて、経済的に厳しい状況にある人々が利用する施設の“食材”として提供する。解凍したチキンは、プロの料理人が調理し、カレーの食材などに使用していました。その後、日本でも同じスキームが構築できないかと検討を重ね、横浜市とも相談をしながら2019年に活動をスタートさせました。
——チキンの寄贈における、コスト面はどのようなものでしょうか?
本多 この取り組みでお渡ししている寄贈用のチキンは、普段使用している冷凍庫を活用。チキンは、袋に入れて賞味期限と一括表示のラベルを貼るだけ。従業員の負担は極めて少ないですし、回収はNPO団体やこども食堂などのスタッフが店舗まで受け取りに来てくれますので、運送コストも発生していません。
ただ、コスト面よりも、私たちとしては、思い入れのあるチキンが誰かの笑顔につながっている喜びのほうが大きいですね。

——調理済みのチキンをこども食堂等に寄贈するにあたり、安全面の確保はどうされているのでしょうか?
本多 安全をいかに担保できるかについてはまず、横浜市の食品衛生課に相談しました。
基本的には、海外の事例やFDA(アメリカ食品医薬品局)、農林水産省のフードバンクの手引き、店舗HACCP(ハサップ:食品の安全性を確保するための衛生管理手法)などを参考にしながら、保管場所や保管方法、提供時には冷凍のままお渡しするなど、提供後の調理までの工程に関しても弊社が定めたルールに沿ってご利用いただく仕組みを構築しました。また寄贈先も、自治体からご紹介のあった団体やこども食堂になります。
なお、チキンをお渡しして終わりではなく、提供先の調理担当者に対してチキンの骨の取り方などの講習会も実施しています。その講習会に参加いただいた団体にだけチキンをお渡しすることで、関わる全員がルールを守り、安全・安心を担保する仕組みにしています。
活動開始から6年間でチキンの寄贈先が14県、約500カ所に拡大
——チキンの寄贈の取り組みは、2019年からスタートされて、現在どのぐらいの規模に拡大しているのでしょうか?
本多 2025年で、スタートから約6年になりますが、横浜市の伊勢佐木町店1店舗から始まった活動が、現在では14県、約500ヵ所のこども食堂等にチキンを寄贈するまでになりました。
この活動は強制的なものではなく、活動の趣旨を理解し、賛同したフランチャイズオーナーさまの店舗が積極的に協力してくださっています。私たちの想像以上に多くの方が参加してくださり、取り組みの広がりを感じています。
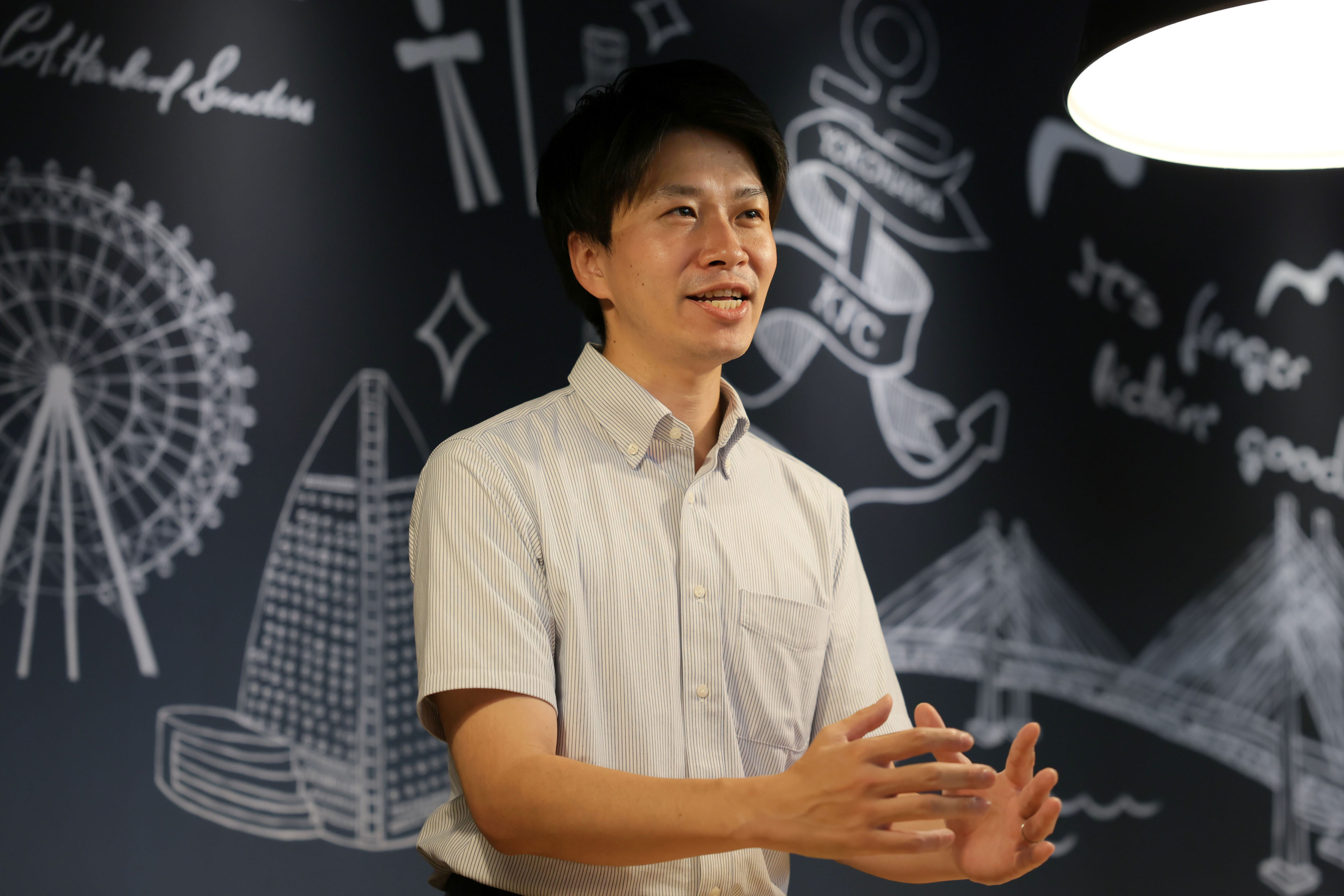
また、店舗従業員のアルバイトは近隣で暮らす主婦や学生の方が多いのですが、自分たちの活動が地域の人たちに喜んでもらえていることを誇りに思っているという声も聞きます。
つまり、店舗従業員からすると「もらってくれて、ありがとう」であり、寄贈先のこども食堂の方からしても「チキンをくれて、ありがとう」。社内外問わず、この活動に関わっている方々に、“しあわせ”が循環していることが、この活動における最大の効果だと考えています。
こうした取り組みは、KFCだからこそできることです。今後も食を通じた社会貢献活動を、未来にわたって続けていきたいですね。
地域を支える信頼のブランドとして持続可能な社会に貢献
——最後に、今後の展望をお聞かせください。
本多 私たちは、これまでも「おいしさ、しあわせ創造」の理念のもと、日々の食を通じてお客さまと、ビジネスに関わるすべての人を“しあわせ”にすることを使命にしてきました。
その軸は今後も変わることなく、地域を支える、信頼できるブランドという役割を果たすことが大きな使命だと考えています。そのためにも、店舗でのお客さまとのつながりを大切にしながら、今後も継続して持続可能な社会に貢献していきます。