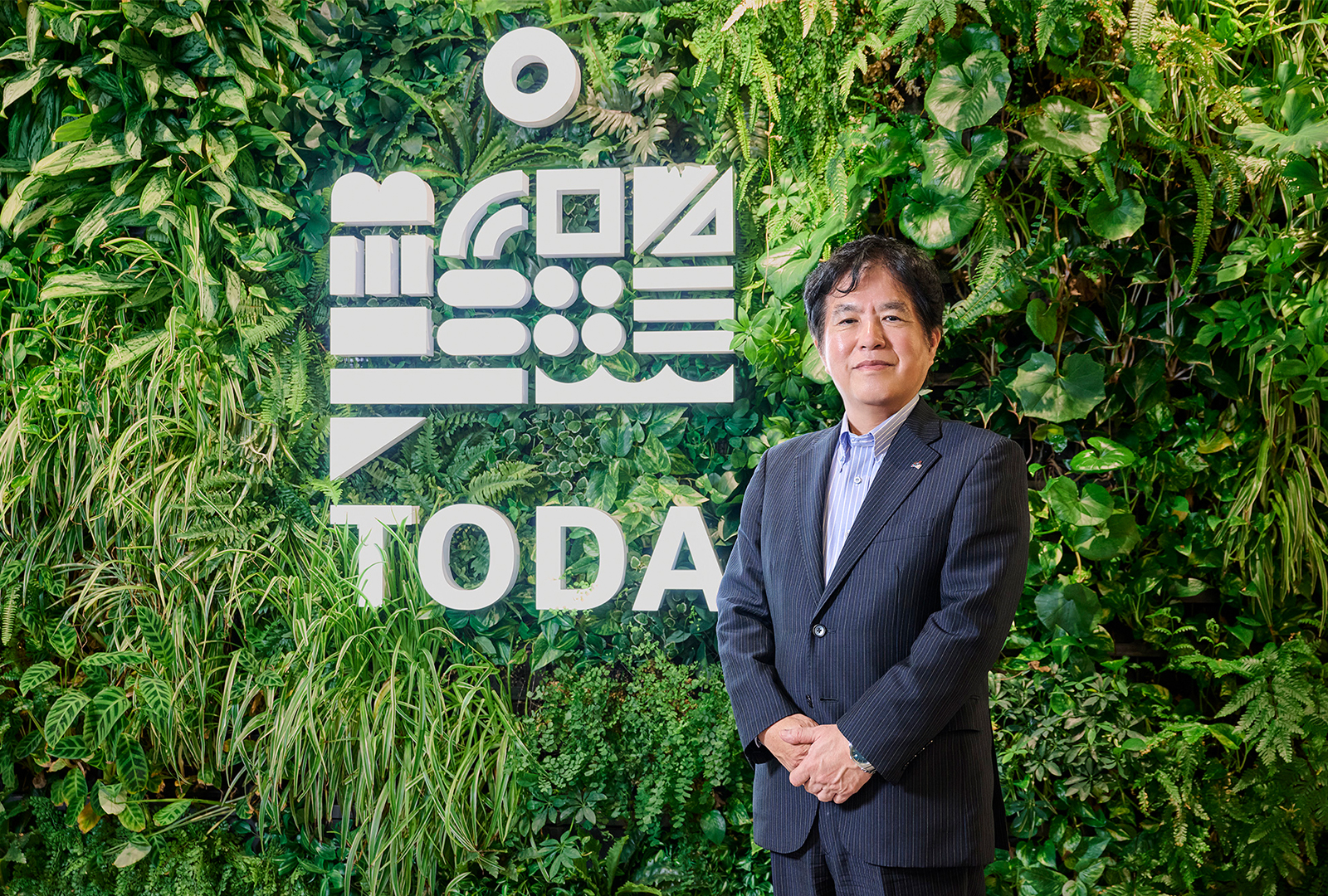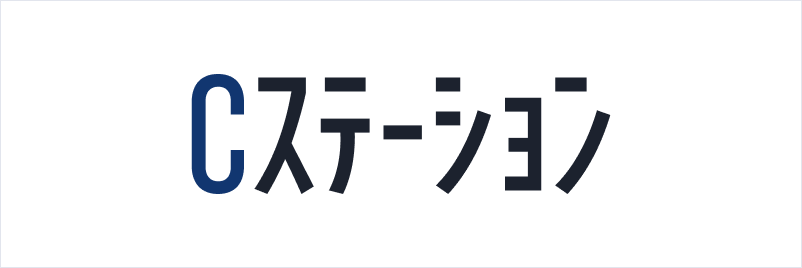エネルギー自給率の低い日本では、再生可能エネルギーの拡大は喫緊の課題といわれています。一方で日本は世界6位の広大な排他的経済水域を有しているため、「洋上風力発電」に大きな期待が集まっています。
戸田建設は、水深の深い海域でも展開できる「浮体式洋上風力発電」に取り組み、長崎県五島市とともに地域一体となりプロジェクトを進めてきました。今回、本プロジェクトと戸田建設のSDGsへの取り組みについて、同社 執行役員副社長 イノベーション本部長の浅野均さんにお話を伺いました。
京都大学と実証実験を重ね、日本初の浮体式洋上風力発電設備の実用化に成功
──まず2016年に、日本初の浮体式洋上風力発電設備「はえんかぜ」が実用化されました。どのような課題があったのでしょうか?
浅野 2007年に模型実験から始め、2016年に、2メガワットの浮体式洋上風力発電設備「はえんかぜ」の実用化に成功しました。2メガワットとは、およそ1800世帯分の発電量をまかなうことができる電力です。
浮体式洋上風力発電の実証事業は、技術的な難しさ、コストの問題もあり、当時、世界でもノルウェーとポルトガルそして日本の3ヵ国でしか行われておらず、先進的なプロジェクトと呼べるものでした。
構造や係留(設備の固定)設計、発電効率への影響など、未確定な技術要素も多く、京都大学と共同で100分の1、10分の1、2分の1とスケールアップしながら解析モデルを構築。洋上の揺れや傾きなども細かく検証しながら構造的な裏付けを固め、設計を進めていきました。


戸田建設グループには土木事業で培った技術開発力があります。2007年に、陸上用風力発電のタワー部にプレキャスト・コンクリート(※)を用いた「STEPSタワー工法」を開発。その技術を応用したハイブリッドスパー構造を小規模な試験機に採用し、技術検証を進めました。
その結果2016年3月、長崎県五島市崎山沖にて日本初の浮体式洋上風力発電設備であり、世界初のハイブリッドスパー型浮体式洋上風力発電施設「はえんかぜ」を実用化することができたのです。
※現場打ちではなく、工場などであらかじめ製造されたコンクリートのこと。
長崎県五島市に受け入れられた秘訣、漁場の再生や地域経済にも貢献
──「はえんかぜ」プロジェクトは、なぜうまくいったのだとお考えですか? 地域の理解を得るために、どのようなことをされたのか教えてください。
浅野 2010年に環境省の実証事業として受託して以降は、浮体部の建設だけでなく、五島市の地元住民への説明会や特許許可の申請など、事業全体のマネージメントも担当してきました。
弊社の浮体式洋上風力発電という再生可能エネルギー事業が、「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロの早期実現を目指す」という五島市の「ゼロカーボンシティ宣言」に合致していたことは大きかったと思います。エリア価値向上にも寄与する事業として、五島市としても非常に積極的に受け入れてくれました。
また、細かく情報を開示するとともに、地域住民との対話を重視したことも効果的だったと感じています。
当時、五島市周辺の海では磯焼け(海藻が急激に減少・消失した状態)がひどく、水産業の持続的発展のために、磯焼けの原因究明と藻場の保全・再生が急務となっていました。
実証事業では、浮体式風車の基礎部に魚が寄ってくる漁礁効果があることが確認されていたので、風車の建設が持続可能な漁業の実現につながる可能性を丁寧に説明。設置することが地域経済や観光産業にも貢献することをご理解いただき、大きな期待と信頼を寄せていただけました。これがプロジェクト成功に大きく起因したと考えています。
(注)2025年8月18日、長崎大学の八木光晴准教授らの研究グループは、長崎県五島市沖で建設中の浮体式洋上風力発電施設に漁礁効果がある可能性を、環境DNA(eDNA)技術を用いて明らかにしたことを発表した。

──地域経済や観光産業面でも具体的な効果が出ているのですか?
浅野 たとえば、「はえんかぜ」を見るために、観光客や自治体関係者の視察などが多く島を訪れ、交流人口が増えました。これにより、賑わい創出ができたと思っています。
また、2018年には、再生可能エネルギーの普及を見据え、市内の企業・団体・個人の出資による地域新電力会社・五島市民電力株式会社が設立。経済発展・雇用促進にも寄与しています。
税収入も大きなメリットといえます。浮体式洋上風力発電設備は「非自航船」といって、自力で航行する能力を持たない船舶。償却資産としての固定資産税が発生するため、将来的に浮体式洋上風力発電設備が増えていけば、それだけ税収入を増やすことができる計算です。
──「はえんかぜ」実用化が、五島市の活性化にも大きく貢献しているのですね。
浅野 現在は8基の浮体式洋上発電設備を建設する「五島洋上ウィンドファーム」を建設し、2026年1月の運転開始を目指してプロジェクトを進めています。
各基が2.1メガワットの発電能力を持し、総発電規模16.8メガワットの発電設備となる予定ですが、2メガワットクラスでは事業の採算性が厳しい面があります。そのため将来的には、15メガワットクラスの風車を動かすことを目標に、大型の風車を浮体に一括搭載できる施工手段の開発にも取り組んでいます。
技術革新とスケールアップしながらの解析モデル作成、実証実験を重ね、2035年には15メガワットクラスの浮体式洋上風力発電を実用化できるよう考えています。
(注)現在、15メガワットクラスの風車の主要メーカーとしては、GE(アメリカ)、シーメンスガメサ(スペイン)、べスタス(デンマーク)などが挙げられるという。

日本近海では「浮体式洋上風力発電」に優位性があるといわれる理由
──浮体式洋上風力発電に注目した背景について教えてください。
浅野 弊社が洋上風力への取り組みをはじめた2007年当時から、化石燃料を使用する火力電力に代わる、水力、太陽光、そして風力といった再生可能エネルギーの重要性は認識されていました。
当時は、再生可能エネルギーといえば太陽光発電が主流。しかし、平地の少ない日本では、太陽光パネルを設置できる場所には限りがあり、また昼夜の発電量に大きな差があるという課題もありました。そこで、安定した電力量が得られ、将来的に発展性が見込める風力発電に私たちは着目したのです。
風力発電は、同じ方向から吹く一定の強さの風があって、はじめて安定的かつ効率的な発電が可能です。陸上の場合は、地形によって風の強さや風向きが変化しやすく、安定的な電力供給が難しいという課題があります。ですが、洋上(海上)には山や谷、建物などの障害物がなく、安定して強い風が吹くことから、洋上風力発電にポテンシャルを感じました。
──プロジェクトの立ち上げ当初は太陽光発電が主流でした。社内の反応はいかがでしたか?
浅野 会社としても風力発電には大きな可能性を感じてはいたものの、まだ実証途中だった浮体式洋上風力発電には確かに懐疑的な意見もありました。
洋上風力発電には、風車を支える構造物を海底に固定する「着床式」と、海上に構造物を浮かせた上に風車を設置して発電する「浮体式」の2種類があります。そのうち浮体式には、陸上風力発電と着床式洋上風力発電にはない大きな利点があり、再生可能エネルギーの利用を促進し、持続可能な社会を目指すための「日本の切り札になる」という確信があったため、繰り返し経営陣に説明し、少しずつ理解を得ていきました。

──浮体式洋上風力発電の大きな利点とは何でしょうか?
浅野 実際に風速の調査などを進めていくと、着床式または浮体式を設置できる可能性のあるエリアは、日本の近海で「着床式1:浮体式9」くらいの面積の割合になることがわかりました。日本の海域では9割が水深50メートルを超えているため、着床式では設置可能なスペースの点で将来的に限界があるのです。しかし、浮体式であれば、より陸地から遠い海域でも設置可能なため、大型の風車を設置しやすいというメリットもあります。
将来的に浮体式洋上風力発電の開発を進めることで、化石燃料を使用した発電による温室効果ガスの排出量削減に大きく貢献できると、プロジェクトの初期に力説しました。
そして2010年、環境省主体の、長崎県五島市で行う浮体式洋上風力発電の実証事業を受託。これを契機に、事業として大きく前進することができました。
国内ゼネコンで唯一、7期連続「CDP 2024気候変動Aリスト」に選定の実績
──戸田建設は1994年に「戸田地球環境憲章」を制定され、建築業界でもいち早く環境課題に取り組んできました。なぜ早くから環境課題解決に取り組んできたのでしょうか。
浅野 今年で創業144年を迎えた弊社は、主に建築、土木、戦略事業の3つの柱で事業を展開しています。戸田建設はゼネコンとして社会課題の解決にどう応えるかを模索しながら成長してきた会社なんです。
環境負荷の少ない施工方法を考案し、建設時の交通渋滞を緩和する道路の工法を考案するなどしながら、事業と環境の両立を図るため、1994年には「戸田地球環境憲章」を制定。2010年には、業界における環境先進企業であることを環境大臣が認定する「エコ・ファースト企業」にも選出。SDGsという言葉が生まれる前から、環境問題を社会課題のひとつとして捉え、真摯に向き合ってきました。
環境評価を行う国際的な非営利団体「CDP(Carbon Disclosure Project)」から、最高ランクの「CDP 2024気候変動Aリスト」に2018年以降7期連続で選定されています。これは、国内のゼネコンでは戸田建設だけです。建設現場はどうしてもCO2の排出量が大きいので、弊社が先陣を切って環境負荷低減に取り組むことで、建設業界全体の脱炭素対策推進に少しでも寄与できればと思っています。
2026年、16.8メガワットの五島洋上ウィンドファームが実証稼働予定。日本全近海に展開し、国内の総電力需要を賄いたい
──今後、浮体式洋上風力発電事業が拡張していくと、排他的経済水域(EEZ)への展開も検討課題となってくるのでしょうか。
浅野 EEZへの展開可能性は浮体式洋上風力発電の発展につながると期待しています。それまでは着実に足元を固めていく必要があります。まずは2026年1月の運転開始を目指している「五島洋上ウィンドファーム」を事業ベースで成り立たせることに全力を尽くしていきたいと考えています。
いまや浮体式洋上風力発電は五島市のシンボルとなっています。洋上ウィンドファーム事業を発展させていくことは、戸田建設にとってだけでなく、五島市の持続可能な未来にとっても欠かせません。
そうした洋上ウィンドファームを日本全国に増やすことで、日本社会のサステナビリティに貢献できると考えているわけです。NEDOの試算では、日本全国に設置可能なエリアのすべてに浮体式風車を設置すると、じつに日本の総エネルギー需要の2倍ものエネルギーを得られることが分かっています。
これからも環境課題解決のトップランナーを目指し、事業を通じて環境負荷低減と地域社会の発展に貢献していきたいと思っています。